Purple Days

L to R:石坂翔太(key)、吉田ワタル(vo)、鈴木俊彦(g)
吉田ワタル(vo)、石坂翔太(key)、鈴木俊彦(g)の3人で構成されるデジタル・ロック・ユニット、Purple Days(パープル・デイズ)。2月のメジャー・デビューを目前に控え、プレ・デビュー・シングル「sayonara」を、1月27日にTSUTAYA限定でリリース!
石坂翔太:最初に僕がギターの俊(鈴木俊彦)を誘ったのきっかけです。メジャー・デビューに向けて本格的に音楽活動をやりたいなと思って。それからしばらくして友人にワタル(吉田ワタル)を紹介してもらって、3人が集まるという形になりました。
石坂翔太:そうですね。出会いは高校生くらいで、その時は自分のデモのためにギターを弾いてもらったり、逆に僕が俊のバンドを手伝ったりといった感じで。
鈴木俊彦:音楽を通じて出会ったんですけど、出会ってから3年くらいは一緒にバンドをやろうとか、固定の形ではやったことはなかったんです。軽い気持ちで、お互いちょっと手伝う程度でした。
吉田ワタル:バンドは一応やっていたんですけど、プロでやっていきたいという気持ちはありませんでした。誘いを受けた時は、美容師の免許を取る学校にいて、卒業間際だったんです。だから、悩みに悩んで。結果、今ここでバンドをやっているんですけど。
鈴木俊彦:なかったですね。翔太と2人で「ヴォーカルいないよね」って、いろいろな友人に声をかけていたんです。「いい人いない?」って写メを送ってもらったりして。そんな中でワタルと会って、その日に何曲か歌ってもらって、キャラもいいし声もいいなって。じゃあ一緒にやってもらえないかという感じで。
吉田ワタル:そりゃ、メチャクチャとまどいましたよね(笑)。2人とも音楽を昔からやっているじゃないですか。僕の周りにもバンドをやっている人はいたんですけど、音楽ひと筋という人があまりいなかったので。性格とか雰囲気とかも僕の周りにはいないタイプの2人で、まずそこに馴染むのにちょっと時間がかかりました。それでも、とまどいはありつつ、2、3ヵ月くらいで慣れていって、言いたいこともお互いに言えるくらいの仲にはなっていきました。
吉田ワタル:今作にも収録されている「Shine Of Love」という曲を翔太がつくっていて、この曲を聴かせてもらった時に、めちゃくちゃ僕に響いて。こういう曲をつくれる人がいるバンドだったら、“やる価値があるかもしれない!”と思ったんです。
石坂翔太:僕自身、昔からずっと音楽をやっていて、バンドを組んでライヴをやっていたんですけど、自分がリーダーじゃなかったこともあって、好きにできないというか、あまり意見が反映されることがなくて。それならば、自分でつくって、やりたいことをやっていこうと思ったんです。ただ、やるからには絶対に売れたいし、プロになるんだという決意がありましたね。
吉田ワタル:そうですね。もう2人に身も心も委ねました。本当に2人とも音楽以外のことをやる気が全然ないんですよ(笑)。
吉田ワタル:“Purple”というのは、そのまま“紫色”のことなんですけど、昔はその紫色を出すために植物を使っていたそうなんです。その植物というのが、群れになって咲く花だから「群ら」「咲き」。その語源に惹かれたのがひとつと、紫という色自体にも、高貴な色だったり、神秘的な色だったり、そういう意味があるので、ちょっと特別感があるかなと。そして、ファンになってくれるみんな、聴いてくれる方も含めて、いい意味で“群れて咲ける日々”をつくっていけたらなという意味で“Days”をつけて、“Purple Days”にしました。
石坂翔太:音楽をはじめた頃は、高校生バンドのようなものをやっていたんですが、なんかちがうなって感じて。それで、さっきの話にもつながるんですけど、僕はデジタル・ロックが好きだから、自分でやっていきたいと思うようになりました。
鈴木俊彦:ないですね。
吉田ワタル:自分でやったことはなかったですね。ただ、意識的に聴いてはいなくても、やっぱり子供の頃から耳には入ってきていたので、馴染みやすかったです。
鈴木俊彦:ウチらが小学生とか中学生のときに流行っていたようなサウンドだったりしますし。
鈴木俊彦:いい意味でのギャップはありましたね。デジタル・ロックといっても、ロック感を出していくのがギターの役目でもあるので、その作業がこんなに楽しいんだという気持ちはありました。
吉田ワタル:結構、難しいなっていう印象でしたね。ノリを出さなければいけないけれど、早い曲が多かったり、キックの音が前面に出ていたりするので。少しでもズレちゃうとうまく表現できないし、レコーディングで何回も録り直したり、そういうところでの葛藤はいまだにあります。
石坂翔太:作曲に関しては、楽器の2人がつくって、その曲をワタルに聴かせて作詞はおまかせという。曲を2人で一緒につくることはあまりなくて、どちらかがつくって投げるというスタイルですね。
石坂翔太:僕の中では“どこか懐かしい中にデジタル感を入れていく”というのが、テーマとしてありますね。全部をデジタルにすればいいというわけではなくて、懐かしいメロディやアレンジを持たせたまま、それでいて古くさくならないっていう。それが微妙で難しいんですけど(笑)。そこは自分の感覚を信じて、その辺のバランスを心がけてます。
鈴木俊彦:個人的にはデジタルの中に、ロックをいかに入れていくか。あとは自分たちが普段聴きたくなるものというか、たとえば電車の中でもいいんですけど、そういう時に自分たちの曲を聴こうと思えるような曲をつくることですね。
吉田ワタル:基本的に曲が先なので、それを聴いてからのインスピレーションですね。曲にもよるんですけど、メロディがわかりやすくて、スッと入ってきやすいので、歌詞もそれに合わせたいなというのがあって。プラス、歌詞を通しで聴いてた時に、ちゃんと意味があって、自分の気持ちを伝えられるように心がけてます。
石坂翔太:僕は小さい頃からTMネットワークがすごく好きで影響されているので、いまだに聴きますね。
鈴木俊彦:僕は洋楽のハード・ロックが好きですね。僕自身ギターをやるので、ギタリストが前に出ているようなオジー・オズボーンとか。あとは、ロックだけではなくて、ブルースとかルーツ・ミュージックも聴いています。
吉田ワタル:僕は2人のように“これを聴く”というよりは、結構いろいろなジャンルに手を出していて。でも、最近は歌のあまりない曲を聴くことが多くて、プロディジーだったり、ハドーケン! だったり、そうかと思ったらストロークスを聴いてみたりとか。ジャンルで好きというよりも、個々に好きで。その中でたまに邦楽を聴いてみたりすると、そこでの差があったりして、勉強になることがよくありますね。
石坂翔太:やっぱりこれも曲が先にできたんですが、つくった時は“ノリノリでアップ・テンポ”というテーマが自分の中にはあって。歌詞に関しては、ワタルに渡す時に何も指示はしないんですね。それで書いてもらった歌詞が切なくて、こんな歌詞がつくんだなって意外に思いました。
吉田ワタル:最初は本当にインスピレーションで、深く聴かないんですよ。スッと軽い気持ちで聴いた時に生まれるものが、自然な流れだと思っているので。はじめて聴いた時に勢いのある曲なんだけど、すごく切なく感じたんですよね。それはきっとコード進行だったり、メロディだったり、いろいろあると思うんですけど、そういうことを考えずに聴いた時に切なかった。それで最初のメロディにはまるものを考えていったら“sayonara”という言葉が出てきて、実際にはめてみたら、自分の中ですごくしっくりきて。“sayonara”をテーマにして、“俺はどんなsayonaraをしてきたのか”を考えていきました。
石坂翔太:いや、聞いていないです。僕らもはじめて聞きますね。続き教えてよ。
吉田ワタル:いろいろなものにsayonaraをしてきているんですけど、やっぱり書くなら恋愛かなと思ったんですよ。わかりやすさもそうですし、自分の過去の恋愛を素直な気持ちで書けるという意味でも。「sayonara」って別れの曲ではあるんですけど、ちょっと“独りよがりな”別れの曲なんです。どちらかといったら自分から別れを言ったのに、引きずっている自分がいるという、男のわがままさを出したかったんです。だから、聴いた人が「sayonaraって言ってるけど、すげえ独りよがりな歌詞じゃねぇ?」という印象を受けるかもしれないんですけど(笑)、それでもいいやと思っていて。それが自分の素直な気持ちだったので。だから歌詞を書いている時は、恥ずかしい話なんですけど、涙が出てきてしまって。全然引きずってないのに、これを書いた次の日からなんか引きずっちゃって。思い出し引きずりみたいな(笑)。
鈴木俊彦:実際に歌ってもらった時の印象は、キャッチーですごくよかったですね。Aメロとかすごく速いんですけど、言葉数が多くてテンポが速い中に、よくこんなにはめてくるなと。
吉田ワタル:自分でも覚えてますけどAメロを書いていた時に、もう意味がわからなくなっちゃっていて。“この言葉、何行目だっけ?”みたいな(笑)。その繰り返しでしたね。
鈴木俊彦:あれは本当によく書けると思うよ。
石坂翔太:やっぱり僕らが伝えたい曲としても、歌詞としても、一番伝えたいことはフルじゃないと伝わらないと思っているので、フルで聴いてもらって、はじめて「Shine Of Love」が届けられるという感じですかね。今TSUTAYAさんで置いてもらっているフリー・レンタルというのは、そのための予告編みたいな感じなので、ちゃんとすべてを伝えられるのが、すごく楽しみです。
鈴木俊彦:早く聴いてもらいたいですね。
吉田ワタル:僕の中でこの“Love”は恋愛だけじゃなくて、家族愛とか、友人に対する親愛の情とか、そういうすべての感情を指しているんです。特定の人への愛というよりも、自分が人から受けている愛、この2人(石坂、鈴木)からであったり、こうしてしゃべらせてもらっていることも愛だと思うし、そういう気持ちを歌詞にした時に、自分の中でこういう表現になりました。
鈴木俊彦:そうですね。やっぱり自分が、ギタリストものが好きだというのもありますし、今まで憧れてきたギタリストへの憧れに対するプレイでもあります。そういう人たちに自分がなれたらいいなという思いも込めて弾いていて。だから、フレーズもそうですし、ちょっとしたニュアンスにも結構こだわって何回も録り直しましたね。
鈴木俊彦:最初にアドリブであててみて、そこからどんどん形をつくっていったり、曲を何回も聴いて頭の中で歌ったものを弾いてみたり、つくり方はいろいろあります。アドリブでつくったにしても、そこからもう1回ちゃんと考えて、決め込んで弾くことが多いですね。
吉田ワタル:そうですね。ちょうどその頃バンドをやっていく上でいろいろなことがあって、気持ち的にちょっと凹んでたんですよ、3人とも。そのキツい時期に生まれた曲ということもあって、そういう心境の自分に言い聞かせている部分があります。慣れない環境だったり、理不尽なことだったり、それは僕らだけではなくて、たとえば、社会に出ているいろいろな人たちにも当てはまるんじゃないかと思って、歌詞にしてみたんです。毎日同じことの繰り返しで、どんどん弱っていく自分がいるんだけど、そんな日々の中でも成長していかなければいけない。だから♪強くなれ昨日より やさしくなれ今日よりも♪という言葉を大事にして、それを中心に考えていきました。自分に言い聞かせつつ、周りにも共感してもらえるような言葉選びをして書いていったんです。
鈴木俊彦:お互いそういう時期だったからかもしれないけど、俺はすごく共感したんだよね。
吉田ワタル:そう言われて、すごくうれしかったのを覚えていて、俺ひとりじゃないんだなと。その時は2人がどういう気持ちでいるのかあまりわからなかったので、そういう言葉をもらって、俺も俊も、もちろん翔太も一緒だったんだなって思いました。
石坂翔太:いずれの曲も、ものすごくヒットした曲で誰もが知っている。だから、その曲の雰囲気を壊さずに、自分たちなりに崩してアレンジもしていかなければいけなかった。その時に、もとの原曲を聴いて、どこをうまく変えれば、聴いてくれる方たちが賛成してくれるんだろうっていうところを、すごく考えました。カヴァーをすることで批判もあるかもしれないという中で、そのバランスの取り方がすごく難しかったんですが、同時にすごく勉強になりましたね。
鈴木俊彦:今、翔太が言ったこともそうなんですが、大ヒットした曲を改めてちゃんと聴いてみて、曲の構造がすごくよくわかって。こういうリズムに、こういうベースがのって、こういうシンセが…というのを改めて確認できたというか。自分でアレンジして組み立てていく上で、こうなっているんだという。“プロの業”じゃないですけど、そういうのがすごく見えてきて、勉強になるなと思いましたね。
吉田ワタル:キーの高さは自分に合わせてもらっているので問題なかったんですけど、一番感じたのは、高さだけでなく下も広いなと。実際に歌ってみて、女性のヴォーカリストの人はすごいんだなというか、音域が広いんだなという印象でしたね。でも自分自身、原曲の通りに歌うというよりは、自分が思ったように歌っているし、聴き慣れている歌なので歌いやすかったですね。アレンジの難しさはあるんですけど、歌う上では意外とスッと自分なりに声に出せて、やっていてすごく楽しかったです。世代的に今の小学生や中学生は原曲を知らない子もいるかもしれないんですけど、そんな子たちが僕らの無料レンタルを手にしてカヴァー曲を聴いて、いい曲だなって原曲まで聴いてくれたら、僕らとしては、すごく大きな喜びですよね。ただ、そのためには、この素晴らしい曲をいい曲のままカヴァーしなければいけない。そうでないと、いい曲なのに、原曲までたどり着かないじゃないですか。そういう意味での難しさは感じました。
石坂翔太:やっぱり僕と俊が一番やらなければいけないことは、曲をつくることなのかなと。僕らにとってはデビューがゴールではなくてスタートだし、そこから続くかどうかなんてことはわからない。だから、デビューが決まったからこそ、今まで以上にわかりやすい曲、自分たちらしい曲、かつ、みんなが共感してくれる曲をつくっていかなければいけないと思っています。それがプレッシャーでもあり、これからの目標でもありますね。
吉田ワタル:僕は盛り上がっているというよりは、逆にどんどん冷静になっていて。自分とPurple Daysを、デビューというスタートラインに立って見つめ直した時に、自分に足りないものがいっぱい見つかっていて。技術やライヴ・パフォーマンスも含めて、いろいろな意味でのスキル・アップ、もちろん歌詞にしても、クオリティをもっと上げていかなければいけない。何年後かに今の曲を聴いて、“あ、俺、成長したな”と自分でも思えるように、もっと自分を引き締めていかなきゃなと強く思っています。
鈴木俊彦:聴いてもらった人が共感できるような作品をどんどんつくっていきたいです。これからどういう評価を受けるかはわからないですけど、まずはひとりでも多くの人に聴いてもらうというのが目標ですね。

●SINGLE
1.27 On Sale
「sayonara」
Purple Days
NFC1-27259
¥1,050(tax in)
★TSUTAYA限定
★Purple Days
http://purple-days.jp/(PC・携帯)















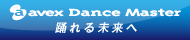
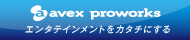
コメント :
コメント投稿: